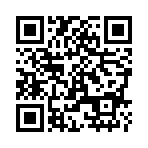2018年05月06日
2018年04月13日
2017年02月25日
2016年11月22日
2016年11月11日
シチメンソウ 「海の紅葉」
東与賀海岸に群生するシチメンソウの紅葉を見に行きました。





シチメンソウは西日本の干潟に群生するアカザ科の一年草で、
塩生植物。10月下旬頃から紅紫色になるため「海の紅葉」と呼ばれている。
12月下旬に芽吹き、秋の紅葉までの色の変化を七面鳥の顔色変化にたとえて名づけられた。





シチメンソウは西日本の干潟に群生するアカザ科の一年草で、
塩生植物。10月下旬頃から紅紫色になるため「海の紅葉」と呼ばれている。
12月下旬に芽吹き、秋の紅葉までの色の変化を七面鳥の顔色変化にたとえて名づけられた。
2016年06月03日
2016年04月29日
2015年05月25日
2015年03月10日
柳川 さげもん
柳川の さげもんに行って来ました、
柳川は川下りなど風情があり好い所ですよー









さげもんの由来ー柳川の初節句に”さげもん”飾りを贈る風習は、
江戸末期頃に始まったといわれています、
女の赤ちゃんが、元気で丈夫にそして一生幸せに育ってほしいと
願いを込めていろいろの縁起物を作って贈りました。
柳川は川下りなど風情があり好い所ですよー









さげもんの由来ー柳川の初節句に”さげもん”飾りを贈る風習は、
江戸末期頃に始まったといわれています、
女の赤ちゃんが、元気で丈夫にそして一生幸せに育ってほしいと
願いを込めていろいろの縁起物を作って贈りました。
2014年09月27日
天山山系
天山に秋を求めてぶらりと行って見る
もうすっかり秋ですね、先日も取った くり、アケビと
今回はヤマボウシの実を取ってきました。
秋ですね

マヤボウシを3kg取れたので課実酒にしました




クリ 今回は少ない


アケビ 今回は20個ほど大きいのが取れた



もうすっかり秋ですね、先日も取った くり、アケビと
今回はヤマボウシの実を取ってきました。
秋ですね

マヤボウシを3kg取れたので課実酒にしました




クリ 今回は少ない


アケビ 今回は20個ほど大きいのが取れた



2014年09月15日
2014年03月03日
2013年09月30日
川上、與止日女神社(よどひめじんじゃ)
ぶらりと昼、與止日女神社に行ってきました、
川上峡を流れる嘉瀬川(かせがわ)には赤い官人橋(川上橋)が架かっており、橋の袂(たもと)に
與止日女神社(よどひめじんじゃ)はあります。
境内には樹齢 1450年の大楠や 慶長13年(1608)に佐賀藩主 鍋島勝茂が寄進した三ノ鳥居などがあります。
そして「金精さん」と言われている怪しげな石があります。 自然石を加工して男性、女性の象徴を模したもので、
本来は性の神であったが、それが生産神、 縁結びの神、性病平癒祈願の神、子宝の神となり庶民の信仰が厚いそうだ。
西暦2014年に、建立1450年記念大祭が盛大に開催されます。









川上峡を流れる嘉瀬川(かせがわ)には赤い官人橋(川上橋)が架かっており、橋の袂(たもと)に
與止日女神社(よどひめじんじゃ)はあります。
境内には樹齢 1450年の大楠や 慶長13年(1608)に佐賀藩主 鍋島勝茂が寄進した三ノ鳥居などがあります。
そして「金精さん」と言われている怪しげな石があります。 自然石を加工して男性、女性の象徴を模したもので、
本来は性の神であったが、それが生産神、 縁結びの神、性病平癒祈願の神、子宝の神となり庶民の信仰が厚いそうだ。
西暦2014年に、建立1450年記念大祭が盛大に開催されます。









2012年10月16日
多久聖廟&西渓公園
多久聖廟と西渓公園に孫連れてぶらりと散策に行く、
天気も良く観光シーズンなので、聖廟には多くの観光客が見えていた、
西渓公園には多くの紅葉があり、11月の中旬には紅葉が美しい、


多久聖廟




西渓公園




西渓公園には入ってすぐ左手に水琴窟があり、いい音を奏でている。
天気も良く観光シーズンなので、聖廟には多くの観光客が見えていた、
西渓公園には多くの紅葉があり、11月の中旬には紅葉が美しい、


多久聖廟




西渓公園




西渓公園には入ってすぐ左手に水琴窟があり、いい音を奏でている。
2012年06月13日
2012年05月12日
小石原。秋月 散策
小石原散策





樹齢200年から600年、約4.68haにわたる375本の杉の巨木群を、
行者杉(ぎょうじゃすぎ)という、行者杉の中でも「大王杉」と名付けられた巨木は、
幹回り約8.3m、樹高約55mあり、林野庁の「森の巨人たち百選」に選定されている。
秋月散策





秋月城黒門

神社の鳥居の上にタラノ木が植わっていた。


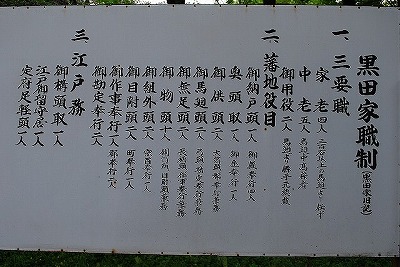
「筑前の小京都」と呼ばれる」秋月には、城下町の風情が残り、
美しい景観や史跡がたくさんある。





樹齢200年から600年、約4.68haにわたる375本の杉の巨木群を、
行者杉(ぎょうじゃすぎ)という、行者杉の中でも「大王杉」と名付けられた巨木は、
幹回り約8.3m、樹高約55mあり、林野庁の「森の巨人たち百選」に選定されている。
秋月散策





秋月城黒門

神社の鳥居の上にタラノ木が植わっていた。


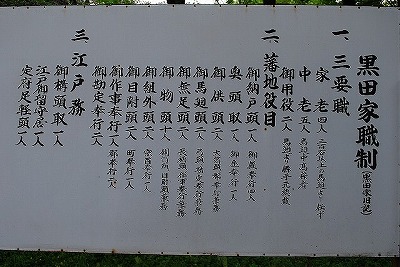
「筑前の小京都」と呼ばれる」秋月には、城下町の風情が残り、
美しい景観や史跡がたくさんある。